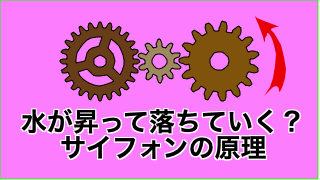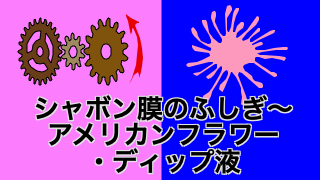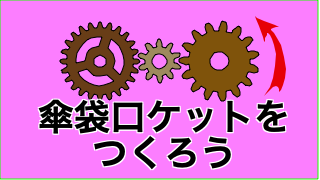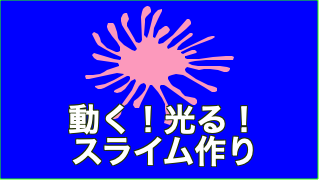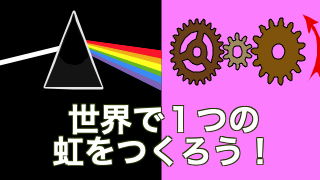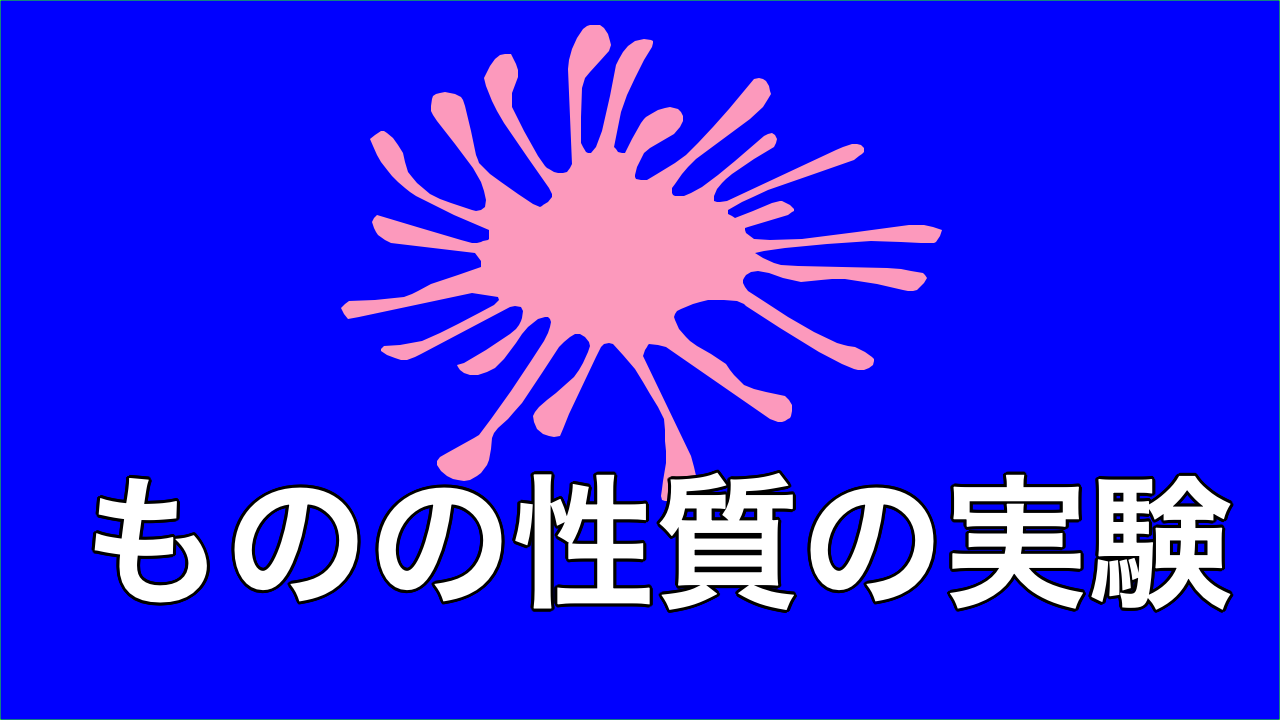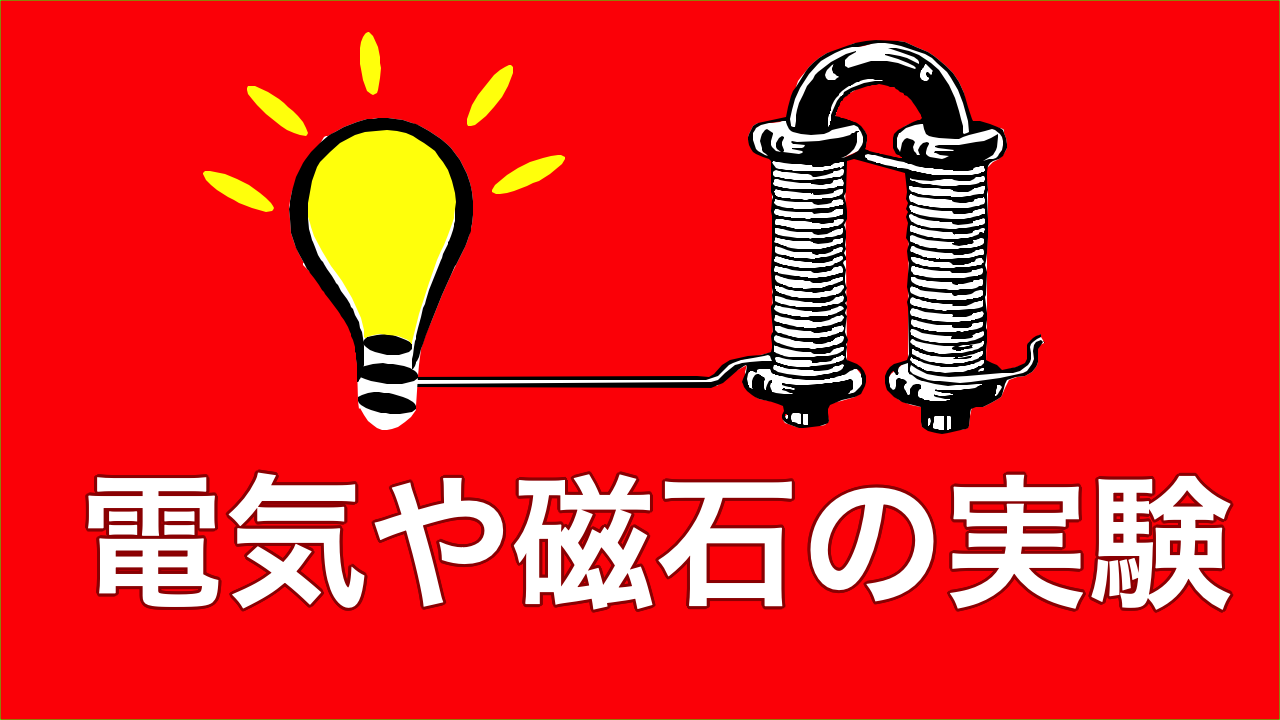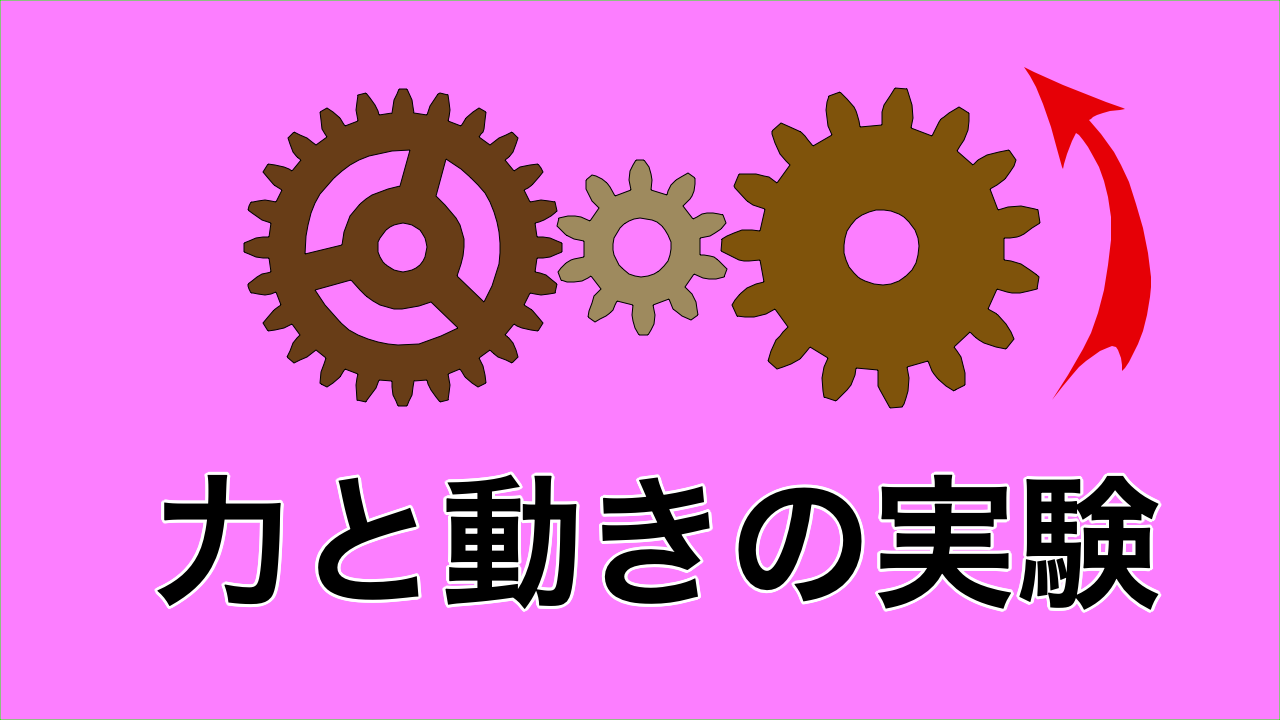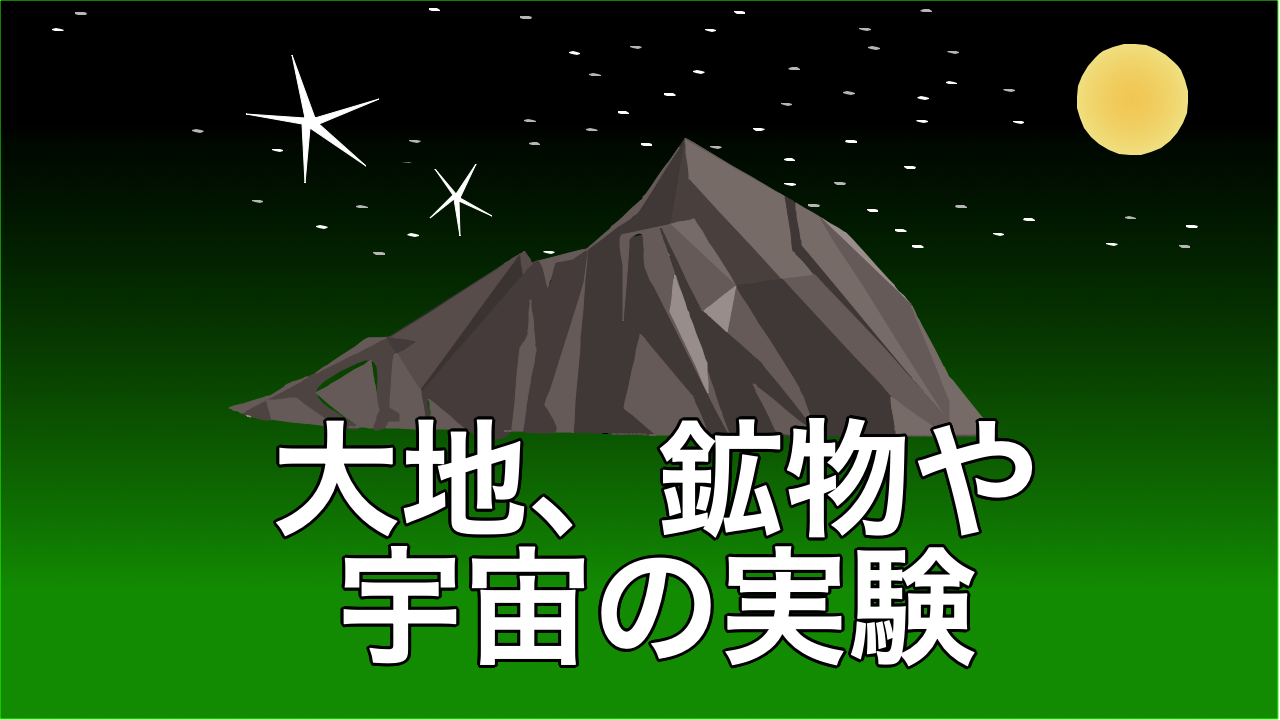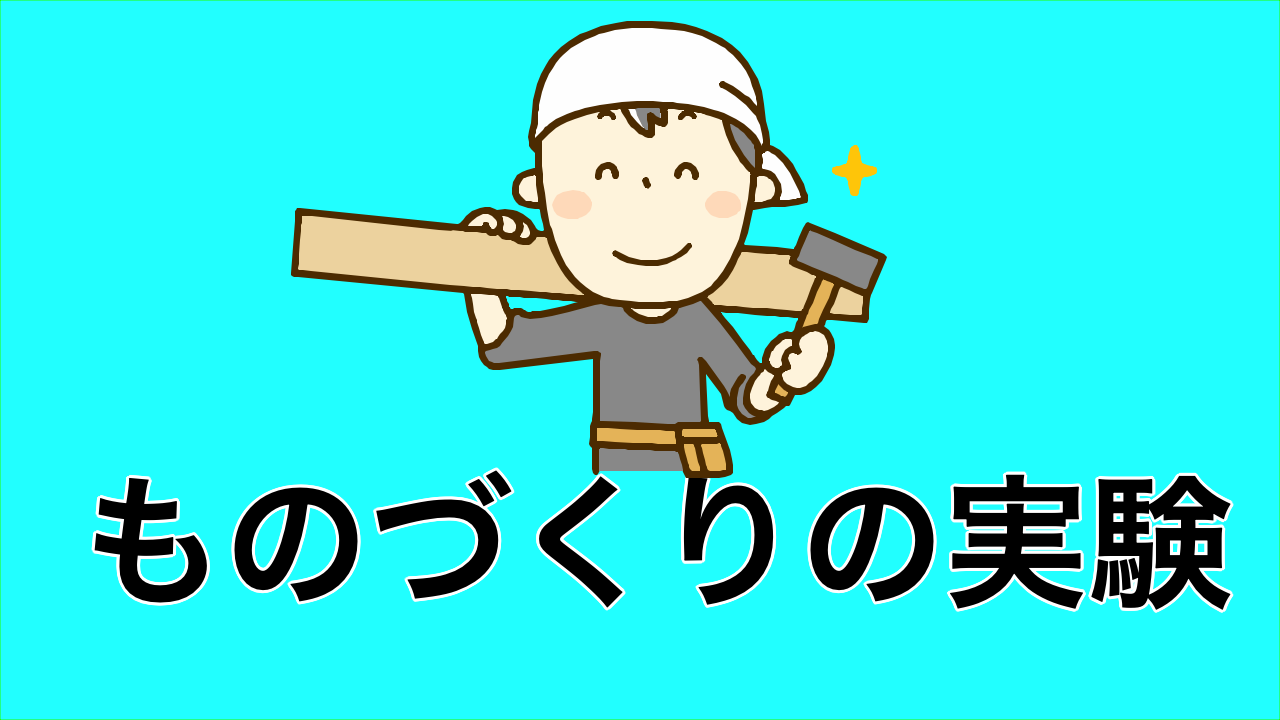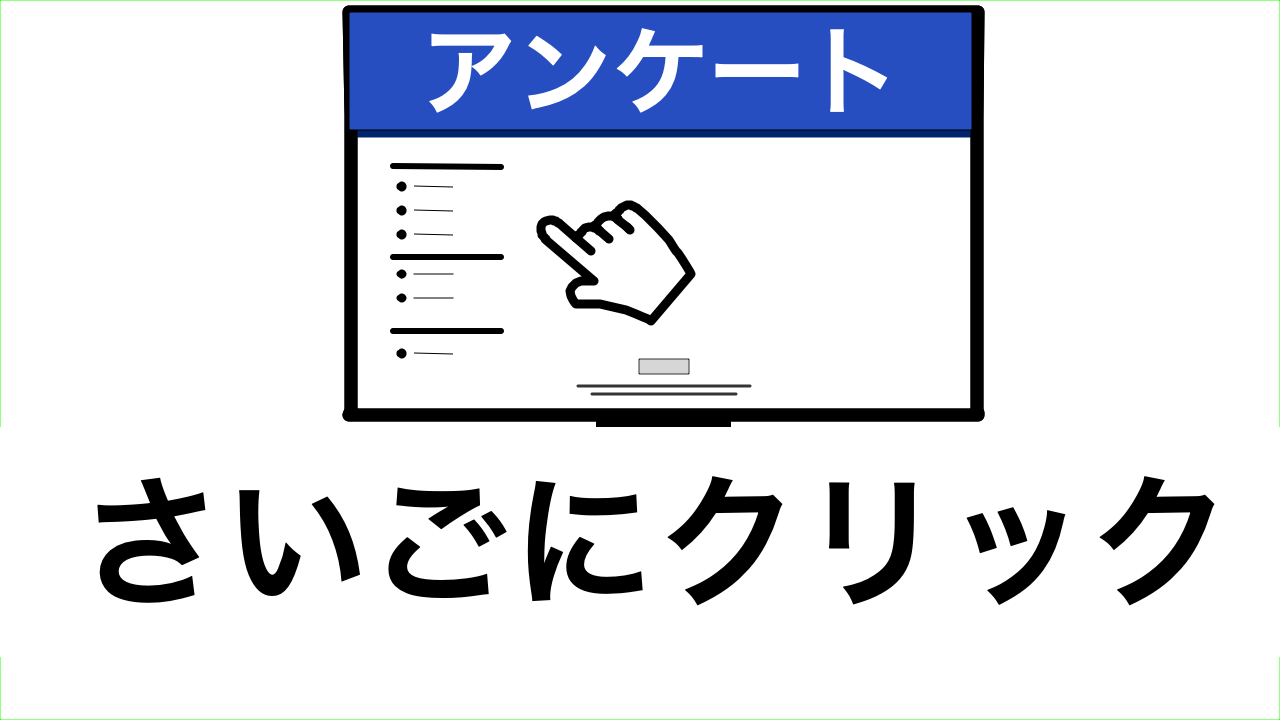ガイドブック
第31回 青少年のための科学の祭典 大阪大会
青少年の創造力とこどもの想像力を育む科学実験と工作教室
基本テーマ「ウィズ/ポストコロナ時代にいきる」
会場 : 大谷中学校・高等学校
31. 手作りバンデグラフ起電機で行う静電気実験
科学部
ボウルやフライパンなど、身近にあるものを使ってバンデグラフという静電気発生装置を作りました。性質が異なる2つのローラーにゴムベルトを掛けて動かすと、密着していたゴムベルトがローラーからはなれるときに電気が乗り移って、上下の電極にそれぞれちがう種類の電気が蓄えられ、調子が良いときは5万Vを超える電圧が発生します。この装置...
PDFでご覧いただけます
32. 浮沈子で浮力の実験を体験しよう!
科学部
水に浮く物と沈んでしまう物の間にはどのような違いがあるのでしょう。身近にあるものを利用して装置を作って、「浮力」について考えてみましょう!...
PDFでご覧いただけます
33. 聴くだけでなく見て確かめられる音の実験
科学部
リコーダーなどの筒を利用した楽器は、筒の長さや吹く強さによって出る音が変わります。このとき筒の中の空気のふるえ方にはどんなちがいが起きているのでしょうか?目に見えない空気の振動を目で見て確かめる装置を作りましたので、出る音と空気の振動の関係を確かめて欲しいと思います。また、空気がなくなると音が伝わらなくなることを確かめ...
PDFでご覧いただけます
34. 水が昇って落ちていく?サイフォンの原理
登美ヶ丘中学校・高等学校
科学部
身近なところで様々な自然法則が確認できます。本年度は、灯油や水そうの水の移し替えに活用されている「サイフォンの原理」を紹介します。...
PDFでご覧いただけます
35. キレイな模様の不思議とは?『万華鏡』
全日制 科学部
穴を覗くとキレイな模様が広がる万華鏡。実は昔、物理学者が実験中に偶然発明したことは知っていましたか?今回は当時の実験テーマだった「偏光」と身の回りにあるビニール素材を利用して万華鏡を作り、自分だけのキレイな模様を観察してみましょう!...
PDFでご覧いただけます
36. シャボン膜のふしぎ~アメリカンフラワー・ディップ液
明星化学部 河原修
本田倫久
松村健
『表面張力』ということばを聞いたことがありますか?水などの液体が丸くなって、その表面積をできるだけ小さくするようにはたらく力のことをいいます。たとえば、シャボン玉が丸くなるのもこの力がはたらいているからです(同じ体積では、球形のときに表面積が最も小さくなります)。また、シャボン膜をいろいろな形の針金わくに張らせると、最...
PDFでご覧いただけます
37. 傘袋口ケットをつくろう
皆さんはロケットがなぜあのような形をしているか不思議に思ったことはありませんか?本当にあの形でないといけないのか…。どうして羽がついているんだろう…。今回は傘袋で小さなロケットを作ってみましょう。どうしたら真っ直ぐ、そしてよく飛ぶのか、試行錯誤しながら君だけの傘袋ロケットを作ってみましょう。...
PDFでご覧いただけます
38. まぜまぜエブリシング
楠山浩二
身近にある物質を混ぜ合わせてみると、泡が出たり、冷たくなったり、一瞬で固まったり...、そんな不思議な様子を体験してみてください。...
PDFでご覧いただけます
39. 動く!光る!スライム作り
渡邉快記
普段遊んでいるスライムに鉄粉や色を付けて、「動くスライム」「光るスライム」を作ります。また、スライムはおもちゃとしてだけではなく、その原理は下の絵のように実は身の回りに多く利用されています。...
PDFでご覧いただけます
40. 世界で1つの虹をつくろう!
理科部実験班 山崎仁太郎
赤・橙(だいだい)・黄・緑・青・藍(あい)・紫(むらさき)の七色の液体を順番に試験管(しけんかん)の中に入れていきます。試験管の中に上手に虹をつくることができるでしょうか!?...
PDFでご覧いただけます
(2022年大会)
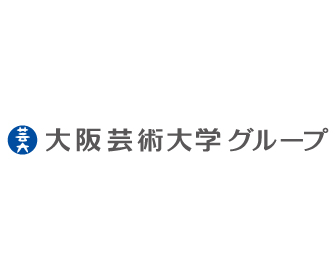



(2022年大会)

(2022年大会)

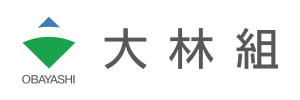




(2022年大会 特別協力)
(2022年大会 特別協力)
- 学校法人大谷学園
大谷中学校・高等学校 - 大阪私立中学校高等学校
理科教育研究会
(2022年大会 特別協力)
- 「青少年のための科学の祭典」
大阪大会実行委員会 - 公益財団法人
日本物理教育学会
近畿支部 - (一社)日本物理学会
大阪支部 - 大阪市立科学館
- 関西
サイエンス・フォーラム - 読売新聞社