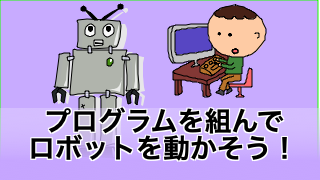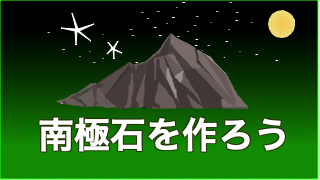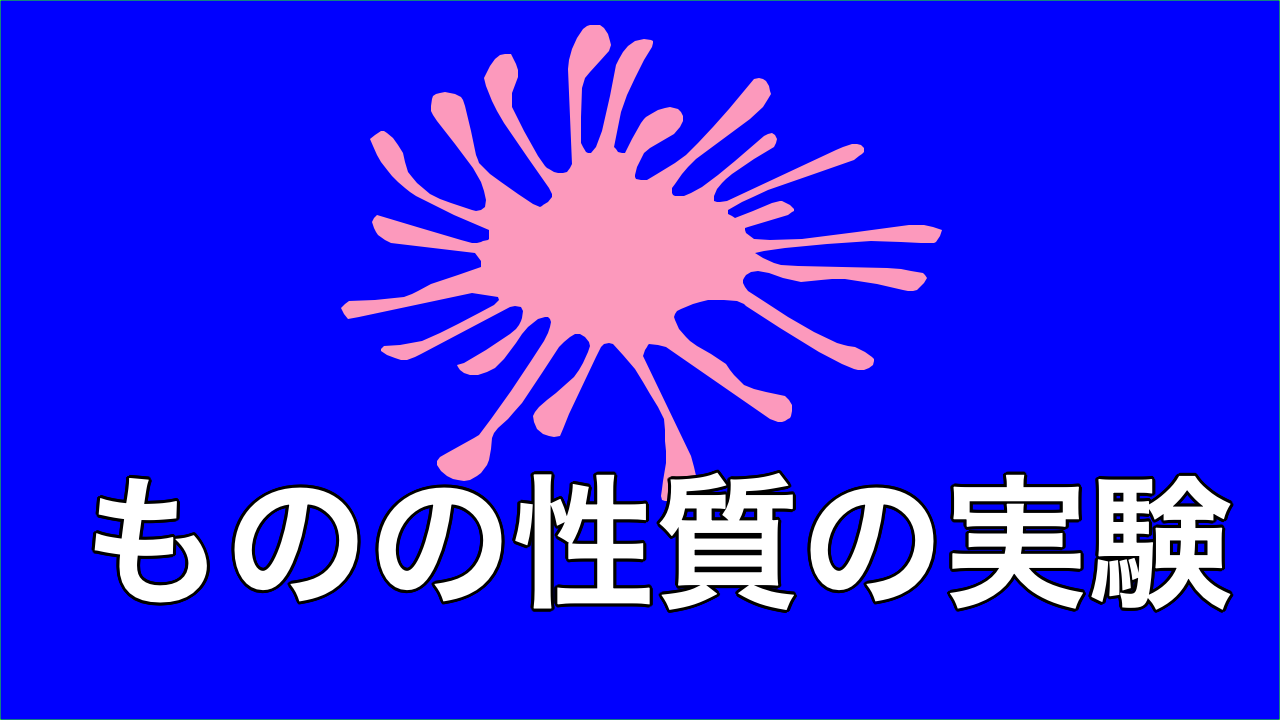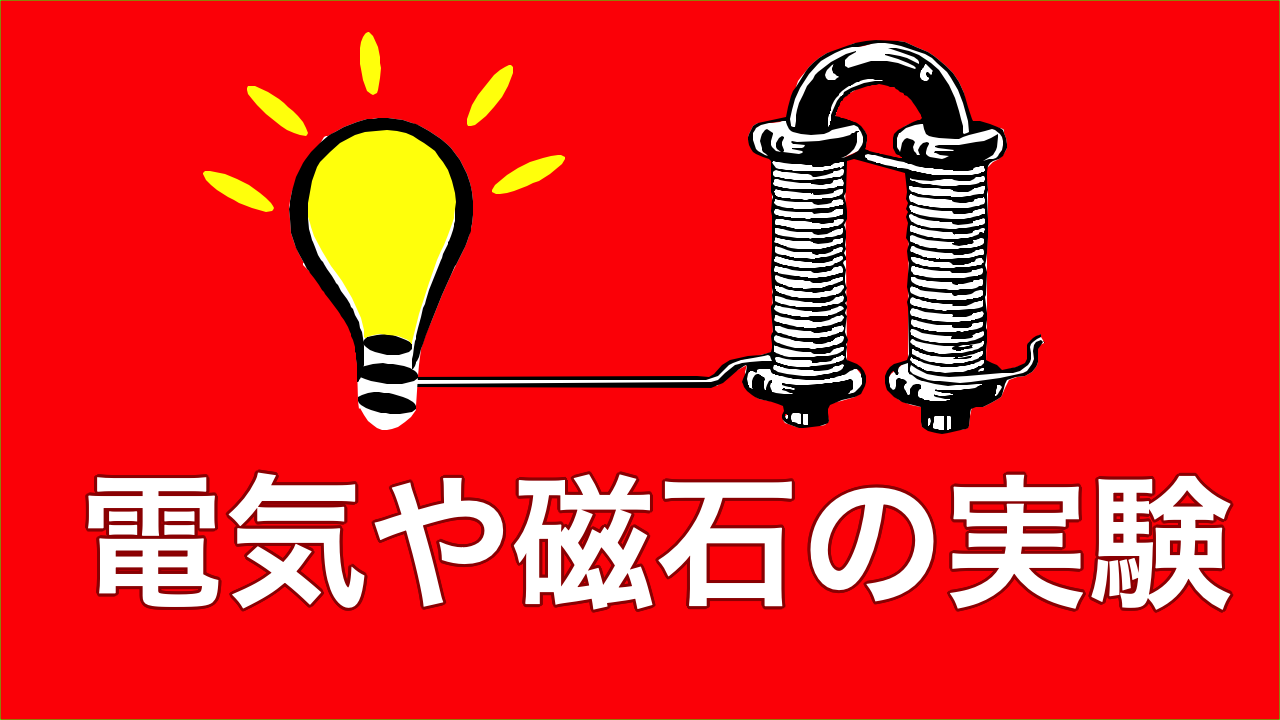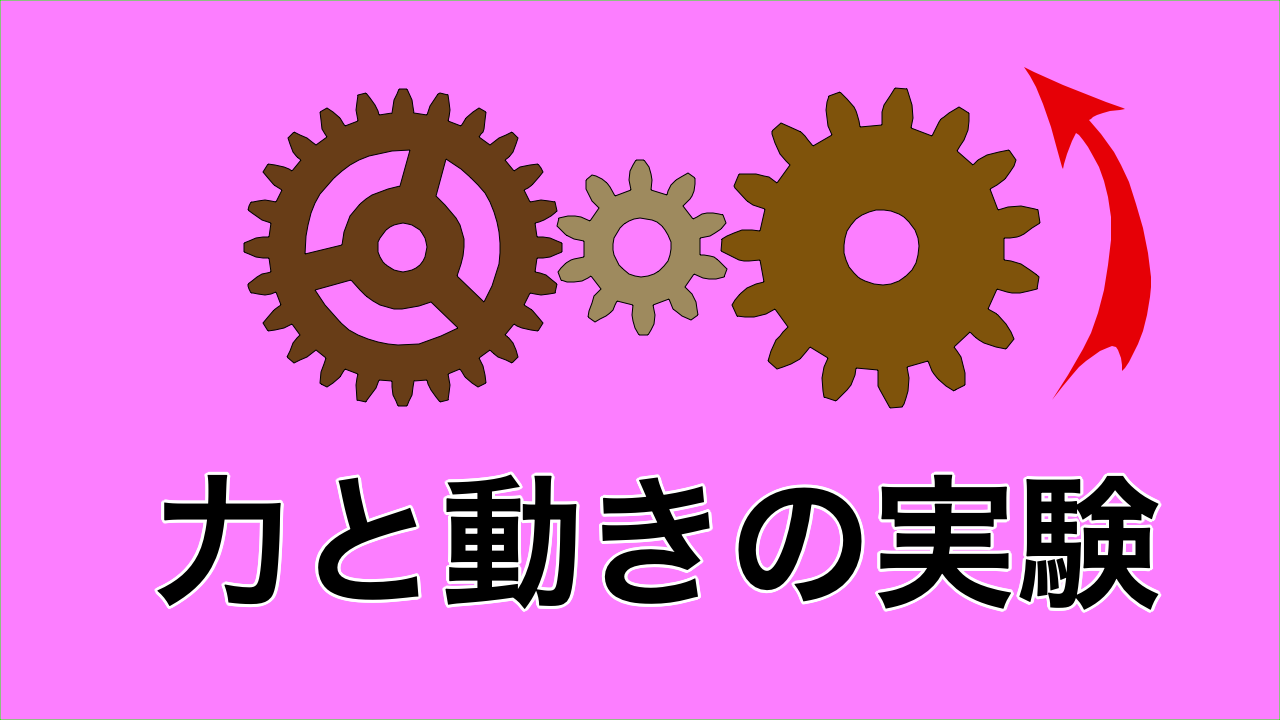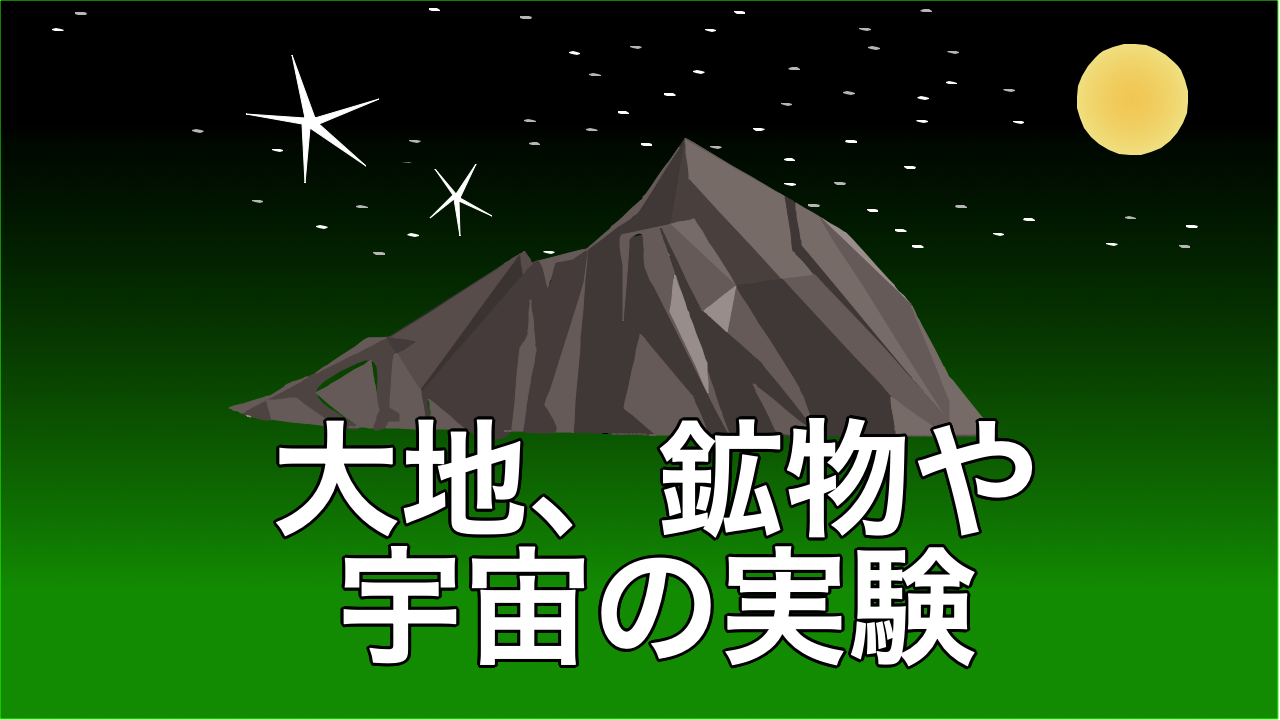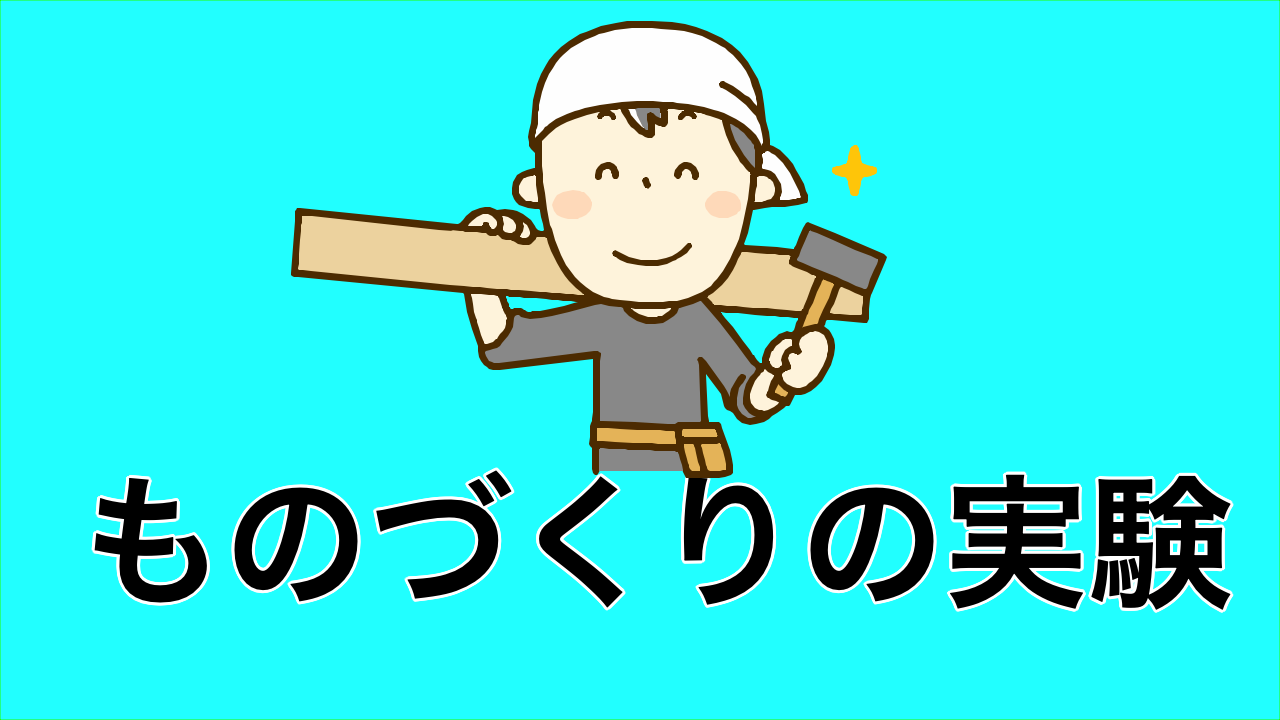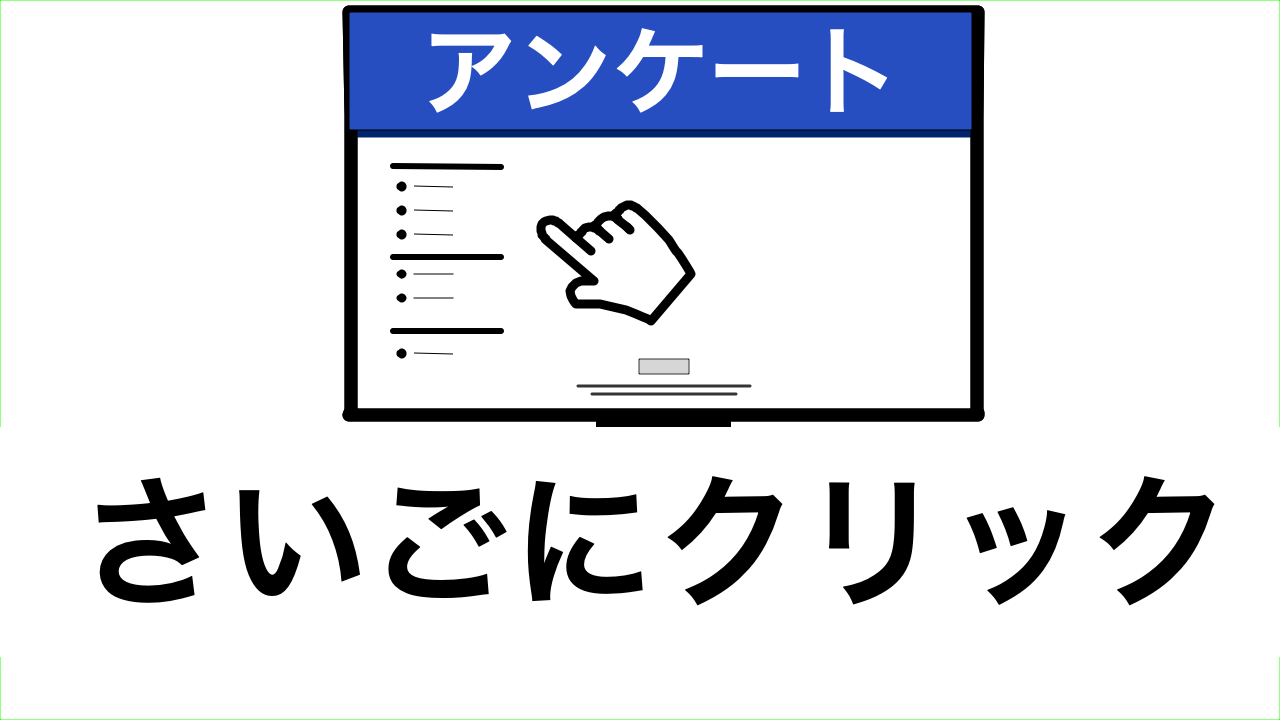ガイドブック
第31回 青少年のための科学の祭典 大阪大会
青少年の創造力とこどもの想像力を育む科学実験と工作教室
基本テーマ「ウィズ/ポストコロナ時代にいきる」
会場 : 大谷中学校・高等学校
11. プログラムを組んでロボットを動かそう!
電気科学部
ペッパーくん、ルンバ、自動運転の車など世の中には自動で動くロボットがあふれています。これらのロボットはどうやって動いていると思いますか?ロボットは自動で動いている訳ではなく、人が事前に指示を与えて動かしています。今回は、タブレットをつかって事前に指示を与えてロボットを動かしてみましょう!...
PDFでご覧いただけます
12. にぼしのかいぼう
科学部
“にぼし”とは、主にカタクチイワシという魚を、煮て干したものを言います。そのまま食べたり料理のだしにしたりしている、身近な食べ物です。生の魚をかいぼうするのは少し抵抗感があると思いますが、にぼしなら大丈夫という人も多いのではないでしょうか。また、今回は刃物を使用しないので、安全にかいぼうができると思います。ヒトと同じ、...
PDFでご覧いただけます
13. 光通信に挑戦しよう
市原義憲
インターネットや電話に使われている先端技術の光通信も原理は、とても単純です。光が音を運んでくる不思議を感じてください。まずは、しくみを知り、通信距離をのばしたり、多重通信もしたりしてみましょう。さあ、あなたも光のメッセージを聞いてみてください。...
PDFでご覧いただけます
14. コウゾから紙をつくってみよう!~和紙づくり体験~
生物飼育部
普段何気なく使っている「紙」が、どうやってつくられているのか知っていますか?日本の和紙は、昔から「コウゾ」「ミツマタ」「ガンピ」などの木の皮の部分を使って作られています。昔ながらの紙づくりを体験することで、物を大切にする気持ちや、使う人、作る人の責任、人の暮らしと自然の関係などを考えてみましょう。...
PDFでご覧いただけます
15. 南極石を作ろう
自然科学部
塩化カルシウム(CaCl2)は吸湿性が高く、クローゼットの除湿剤に用いられています。また、積雪時の融雪剤、豆腐の凝固剤、食品添加物などにも使用されています。「南極石(アンタークチサイト)」は塩化カルシウム六水和物(CaCl2・6H2O)の化学組成を持つ鉱物で、1963年に日本人探検家の鳥居鉄也によって南極大陸のドンファ...
PDFでご覧いただけます
16. 計算神経衰弱
数学研究部
記憶力と計算力をフル活用!トランプゲームの「神経衰弱」に計算の要素を組み込んでひと味ちがうゲームを楽しもう!...
PDFでご覧いただけます
17. マイナス196度の世界
デザイン工学部 環境理工学科
硲隆太 西田哲也
液体窒素を用いてマイナス196°Cの世界をのぞき、常温では見られない現象を体験しよう。例えば、天然ガスは通常気体ですが、マイナス162°Cに冷やすと液体になり、体積が約600分の1となります。この性質を利用して海外から効率的に輸送しています。...
PDFでご覧いただけます
18. サボテンの世界
自然科学部
「サボテン」は、サボテン科の植物の総称で、2000種類以上あります。サボテンの特徴といえば、肉厚のからだとそこから伸びる棘(とげ)です。特に、棘の部分は葉や茎が変化したものと考えられています。今回は、ホームセンターなどでも簡単に手に入る種類のサボテンについて、細部の観察をしてみましょう。...
PDFでご覧いただけます
19. 骨の形
和泉市立鶴山台北小学校 若林雅之
大東市立諸福中学校 堀江貴宏
動物の骨格標本やヒトの人体模型を観察しながら、骨の形の「なぜ」にせまってみましょう。...
PDFでご覧いただけます
20. それがDNAです
自然科学部
近年、新型コロナウイルスの変異株がたくさん出現しています。なぜかというと、変異株それぞれの設計図が簡単に変わりやすいからです。設計図が変わると、ウイルスの形や特徴も変わります。この設計図はDNAやRNAと言われるもので、ウイルス以外に、私たち人間や野菜、果物なども持っています。普段目にすることができないDNAを実験によ...
PDFでご覧いただけます
(2022年大会)
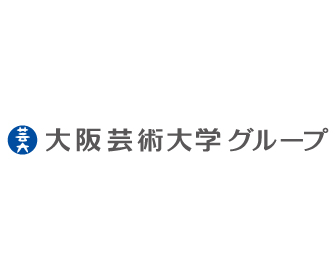



(2022年大会)

(2022年大会)

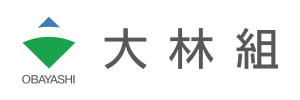




(2022年大会 特別協力)
(2022年大会 特別協力)
- 学校法人大谷学園
大谷中学校・高等学校 - 大阪私立中学校高等学校
理科教育研究会
(2022年大会 特別協力)
- 「青少年のための科学の祭典」
大阪大会実行委員会 - 公益財団法人
日本物理教育学会
近畿支部 - (一社)日本物理学会
大阪支部 - 大阪市立科学館
- 関西
サイエンス・フォーラム - 読売新聞社